近年、地球温暖化の影響で、工場の屋根や建物内の温度が上昇しています。従業員の安全性と生産性を保つためには、暑さ対策が不可欠です。この記事では、暑さ指数(WBGT)、過去の気温変化データ、2025年6月1日に施行された熱中症対策義務化法などの最新情報を交え、遮熱対策についてご紹介いたします。
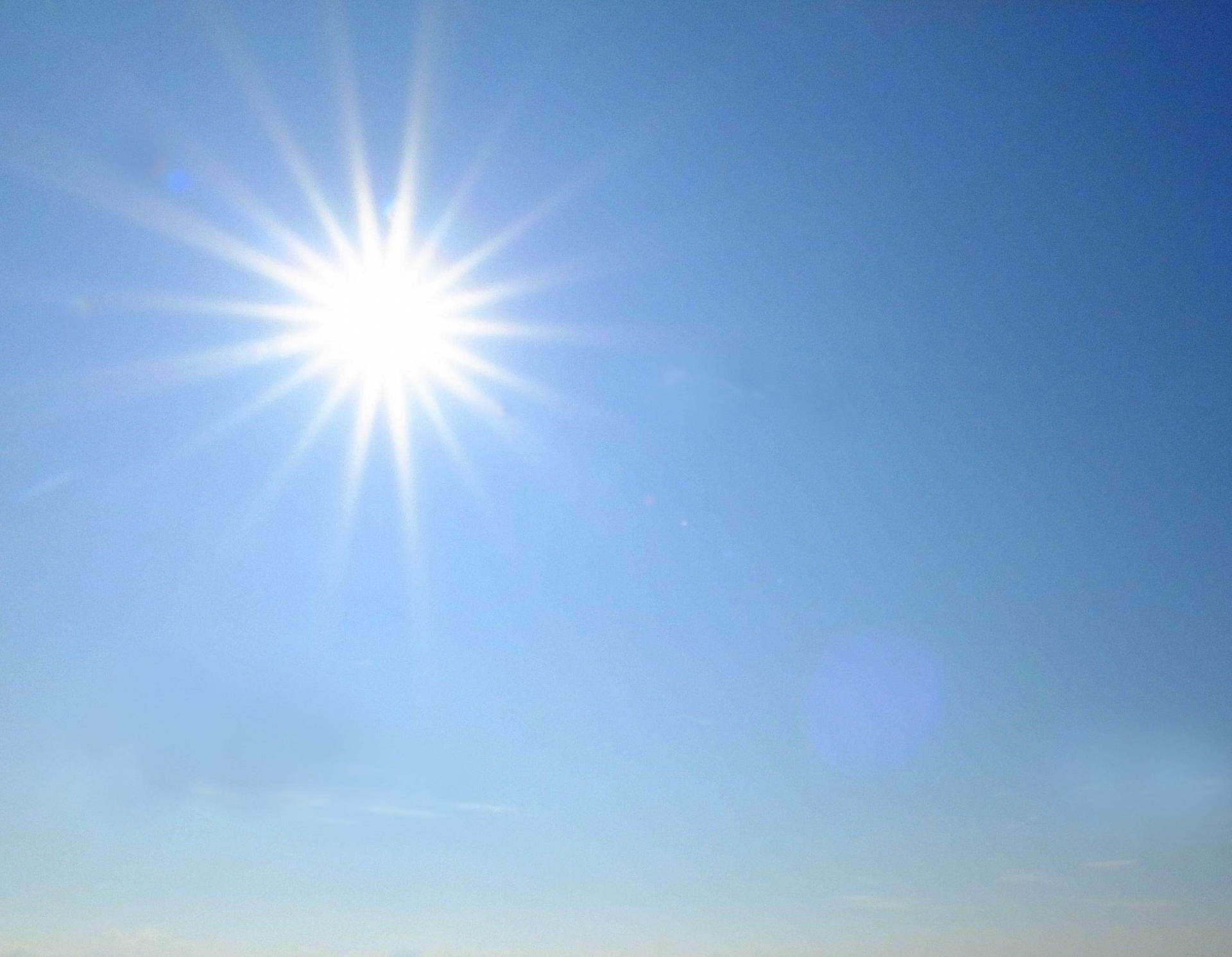
[toc]
温暖化による工場・従業員への影響と気温変遷
過去100年の気温変化による猛暑日の増加
世界の平均気温はおよそ100年間で0.76℃上昇しており、なかでも日本は1.35℃の上昇が見られます。
この変化は、工場内外で見た場合でも当然のことながら温度の上昇を促し、従業員の作業環境に負担をかけています。
日本全国で、35℃以上の日数である猛暑日は100年間で約2.6日増加しています。1995年から2024年の年間平均は約3.0日で、1910年から1939年の平均と比較すると約3.9倍に増加しています。
2025年の夏の暑さ
気象庁は、2025年の夏(6~8月)の日本の平均気温が統計開始以来最も高かったと発表しました。平年との差は+2.36℃となり、これまでの記録だった2024年と2023年の+1.76℃を大幅に上回り、1898年の統計開始以来、127年間で最も暑い夏となります。
工場では、屋根や建物による熱の蓄積でさらに暑さが増すことが懸念されます。
WBGTの定義
WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)は、WBGTは熱中症リスクを把握するための世界的な指標で、1954年(昭和29年)にアメリカで開発されました。気温、湿度、輻射(黒球温度)をはじめ、風や日射を総合的に評価する指標です。単位は摂氏度(℃)で示されますが、熱中症の予防を目的として、人体が熱をどのようにやり取りするかという熱収支に着目して算出されます。
屋外での計算式:WBGT = 0.7 × 湿球温度 + 0.2 × 黒球温度 + 0.1 × 乾球温度
WBGT値の指標として、25℃未満は「注意」、25~28℃は「警戒」、28~31℃は「厳重警戒」、31℃以上は「危険」です。職場で対策をする際には、厚生労働省が提示している「身体作業強度等に応じたWBGT基準値」を参考にすることで、適切な対策を取ることができます。正確な熱ストレスリスクを把握することで、作業時間の見直しや休憩の導入、冷却設備の配置を行い、従業員の安全を確保するために重要です。
「熱中症対策義務化」について
2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正が施行され、すべての事業者に熱中症対策が義務付けられました。
義務化の内容WBGTが28℃以上または気温31℃以上の作業場において、継続して1時間以上行われる作業が対象となります。
事業者の義務
・報告体制の整備: 熱中症の症状がある作業者や、熱中症のリスクがある作業者を発見した場合の報告体制を整備し、作業者に周知すること。
・予防および悪化防止の措置: 熱中症の症状が出た場合に作業者が適切に作業を中断し、身体を冷却し、必要な場合には医療処置を受けられるようにすること。
法改正の背景
すべての産業において、日常業務の中で熱中症の発生リスクが高まっていることを受けて法改正されました。年々増加する高温多湿の環境に対応するため、早期の対策が企業の持続可能な成長に不可欠となっています。
企業が考えるべき暑さ対策:3つの観点
・工場・倉庫の遮熱対策
工場の屋根や壁面は太陽の熱を直接受けます。遮熱塗料や断熱工事などで温度上昇を抑えることが重要です。
・機械・設備の遮熱対策
高温にさらされる機器は故障リスクが高まります。遮熱フィルムや断熱カバーの使用で設備を保護し、工場内の温度を安定させます。
・従業員の暑さ対策
ネッククーラーなどの着用等、高温多湿の中で作業をおこなう従業員の身を守る対策をした上で、WBGTの定期的測定による熱中症リスクの可視化、作業計画の見直し、休憩ルールの設定、社内教育により、相互監視体制を強化することも必要です。
まとめ
温暖化に伴う課題として、「工場」「遮熱」「暑さ対策」「従業員」の安全と生産性の確保が重要です。気温変化データや新法令に基づき、遮熱対策は単なるコストではなく、リスクの回避と業務継続性のための重要な投資です。
弊社では、工場や設備の遮熱対策、従業員の暑さ対策についてもご提案いたしております。 遮熱・暑さ対策について
遮熱対策、暑さ対策についてお気軽にご相談ください。
お問合せはこちらから
文/エネルギー事業部 産業エネルギー課 インサイドセールスチーム

